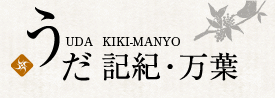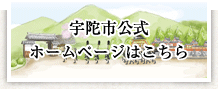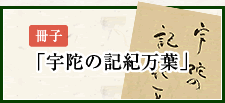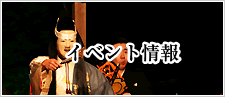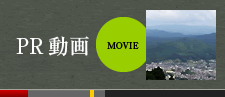ここから本文です。
ヤマトタケルと漆
 鎌倉時代初期までに成立した『以呂波字類抄(いろはじるいしょう)』に引くところの「本朝事始(ほんちょうことはじめ)」に、「ヤマトタケルが宇陀の阿貴山(あきやま)に猟した時に、漆の木を見出して漆部(うるしべ)の官を任じた。」という伝承をのせています。
鎌倉時代初期までに成立した『以呂波字類抄(いろはじるいしょう)』に引くところの「本朝事始(ほんちょうことはじめ)」に、「ヤマトタケルが宇陀の阿貴山(あきやま)に猟した時に、漆の木を見出して漆部(うるしべ)の官を任じた。」という伝承をのせています。
ヤマトタケルが、宇陀の阿貴山で狩猟をしていた時、大きな猪に矢を射ましたが、止めを刺すことができませんでした。そこで近くにあった木を折ってその汁を矢の先に塗り込めて、再び射ると、見事に大猪を仕留めることができました。木汁で手が黒く染まったヤマトタケルは、部下の者に命じてその木汁を集めさせ、持っている物に塗ると、黒い光沢を放って美しく染まりました。これが「漆塗り」の始まりとなります。
この発見の地が漆河原(うるしがわら)と呼ばれるようになり、宇陀に「漆部造(ぬりべのみやつこ)」が置かれました。宇陀市大宇陀に嬉河原(うれしがわら)という地名がありますが、これは、「漆河原」が変わったものと考えられています。
お問い合わせ